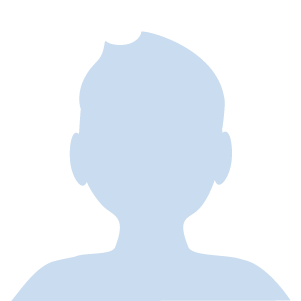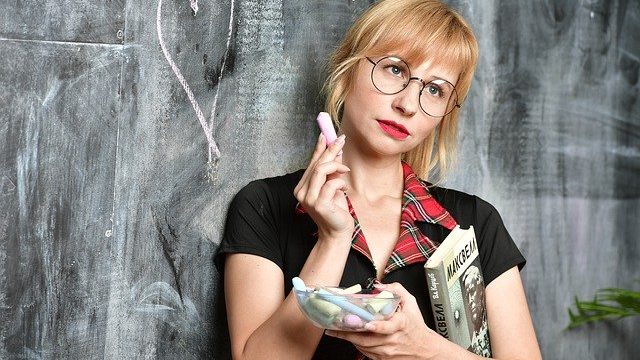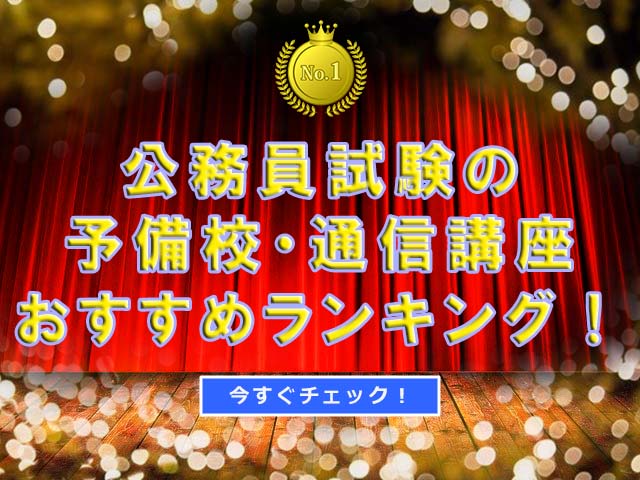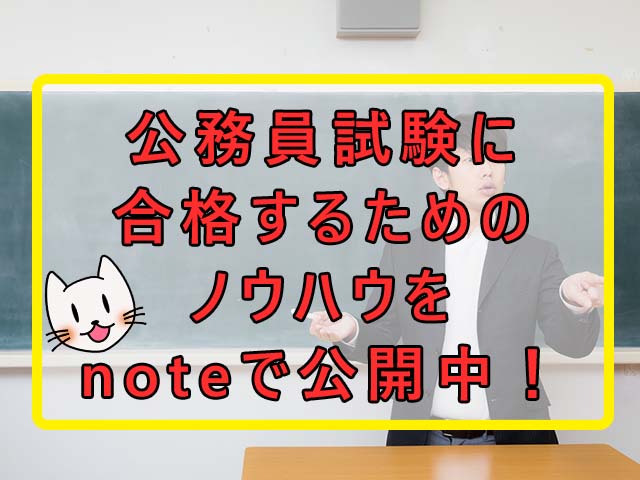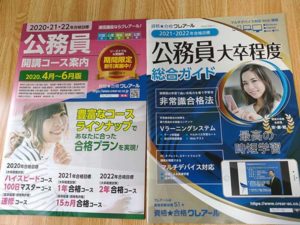元県庁職員おすすめの通信講座をご紹介
今は自宅にいながらネットで学習できる環境がかなり進化しています。
そのため、自分のライフスタイルや予算に合わせて通信講座を選択する人が多くなっています。
費用も安いですし、いつでもどこでも何度でも見直せる通信講座のオンデマンド学習は予備校よりもかなり便利です。
そんなおすすめ通信講座について興味がある方はぜひ以下の記事を見てみてください。
公務員試験を受験しようとしている人にとって、意外と頭を悩ませるのが小論文だと思います。
公務員試験の小論文は対策のしようがないと思っている人が多いのではないでしょうか。
実際僕も、公務員試験を受けた時には小論文は意外に苦戦しました。
しかし、国家公務員一般職や地方上級に合格することができたので小論文の書き方自体は正しかったと思います。
そんな僕が、公務員試験の小論文のテーマや書き方、おすすめ参考書について紹介します。
公務員試験の対策をしっかりできるおすすめの予備校はこちらの記事でまとめています。
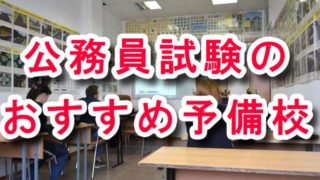
目次(もくじ)
公務員試験 小論文 テーマ
公務員試験の小論文のテーマは、だいたい注目されるネタが決まっています。
というのも、抱える問題というのはどの自治体も共通して同じなことが多いからです。
自治体の立地や特徴によって、多少その変化があるくらいでしょうか。
たとえば観光に強い自治体は、観光が小論文のテーマになりやすかったりするといった具合ですね。
全国の自治体を見てみると、やはり取り上げられることが多いのは少子高齢化問題や、人口減少問題といったテーマです。
また、最近ではワークライフバランスや働き方改革などの言葉が出てきましたが、こういった問題も取り上げられるようになっています。
そして、災害が多くなってきているので、防災関連の内容も注目されやすいです。
外国人誘致など観光に力を入れている自治体では、観光振興がテーマになることも多くあります。
そして公務員は、そういった人間に直接関連する問題だけではなく、環境対策などの問題も抱えています。
たとえば温暖化対策だったり、農林水産の振興など自然に関することをテーマに扱うこともあります。
このように見てみると、
と思う人もいるかもしれません。
まさにその通りで、公務員というのは行政が関連するあらゆる問題を、普段の業務として扱っています。
そして数ある部署のうちのひとつの部署にあなたが配属され、こうした問題を解決していくというわけですね。
小論文のテーマというのは、公務員が今抱えている問題がそのままテーマになることがかなり多くあります。
公務員試験 小論文 書き方
ここまでで公務員試験の小論文でどのようなテーマが出されるのか把握できたので、次は書き方について紹介したいと思います。
試験の小論文の書き方というのは、だいたいパターンが決まっています。
というか、これを外すとあまりまとまりのない話になってしまい、減点される対象になってしまいます。
小論文はまず定義付けしてから背景について解説します。
小論文の書き方 定義
小論文は、問題を定義するところから始めてみましょう。
定義というのは、与えられたテーマが「どのようなものなのか」というのを説明することです。
今から私はこの問題のどういう事について解説します(小論文で述べます)ということを宣言するというわけですね。
例えば少子高齢化というものがテーマに与えられたとしたら、少子高齢化とは何かということを自分の口で説明する感じです。それを定義といいます。
小論文の書き方 背景
そしてその問題がどのようにして起こったのか?という背景を説明します。
少子高齢化の場合だと、少子高齢化になった理由を解説すればいいということですね。
これを背景といいます。
背景を説明したら、問題提起をして解決策を示し、自分の結論を解説すれば小論文は完成です。
小論文の書き方 問題提起
この問題定義はどういうことかというと、このまま問題を放置するとどのような未来になってしまうのか?という問題を呼びかけることです。
現状すでに問題になっていることでも構いません。
このまま放置するとどんなまずいことが起こるのかという問題を、読み手に投げかけます。
たとえば少子高齢化なら、このまま放置されるとどういった問題が起こるのかということを伝えるというわけですね。
小論文の書き方 解決策
ここまで書いたら、後はどのようにしてその問題を解決するのかを解説します。
少子高齢化問題なら、若年夫婦の世帯を自治体に呼び込むような施策を実施するなどですね。
ただ、解決策は具体的に書く必要がありますので注意してください。
たとえば18歳以下の子供の医療費の無償化や、子供がいる世帯の税金の減免などが考えられます。
こういった解決策については、すでに実施している自治体を参考にすると、どんな対策があるか知ることができますよ。
小論文の書き方 結論
そして、最後に結論を書いて終了です。
これまで書いてきたことをざっくりまとめて、~~だから〇〇するべき。というような感じでまとめます。
初めて公務員試験の小論文のテーマや書き方について知った人は、難しく感じるかもしれません。
しかしがこの小論文というのは、これらの項目について順番に埋めていけば自然と文章が仕上がるようになっています。
ある意味、この五つの形を覚えてしまえば簡単に小論文を書いていくことができます。
公務員試験 小論文 コロナ
2020年以降は、これまでの公務員試験の小論文とは少し傾向が異なり、新たなテーマとしてコロナ問題が取り上げられる可能性が高いでしょう。
コロナ問題は今もなお行政も必死に対応しているところです。
ということは、どういった対策が考えられるか?というテーマで取り上げられる可能性は高いと言えるでしょう。
そして、公務員試験の小論文の対策としては、ひたすら数をこなすということが大切です。
まず小論文の書くということに慣れなくてはいけません。
公務員試験 小論文 文字数
公務員試験の小論文の文字数は、大体800字から1200文字ぐらいになることが多いでしょう。
自治体によってまちまちですが、だいたい原稿用紙が2枚から3枚とイメージしてもらえばいいです。
文章を書き慣れていなかったり、読書感想文が嫌いなタイプの人であれば、この文字数を見て多すぎると思うかもしれませんが、書いてみると意外と少ないものです。
書きたいことを全て書いていると、全く用紙が足りなくなってしまうので、注意が必要です。
小論文の書き方として大切なのは、まずは全体像を把握して原稿用紙のどれぐらいの量に、この書きたいことを納めるのかという割り振りを、ざっくり考えることです。
そうすれば文字が少なすぎることもありませんし、多すぎて書ききれないということもありません。
小論文で足切りにならないためには、文字数は8割程度は埋めたいところ。
逆にいうと原稿用紙が足りないぐらいまで書いてしまうと、それはそもそも小論文の条件を満たしていないことになるので、足切りの対象になります。
なのでまずはしっかり文字数に収めること。そして8割を超えて、構成を守って書き上げること。
これらを意識すれば最低限読んでもらえる小論文になります。
公務員試験 小論文 参考書
公務員試験の小論文のおすすめ参考書はこちら。
体系的にまとめられていて、ブログやネット上にある情報よりも濃い内容で書かれてます。
小論文対策だけでなく、集団面接にも使えるテーマを勉強できて便利ですよ。
例年発行されていますが、評価も高くわかりやすい解説なのでおすすめです。
そして小論文は、ただひたすら練習して慣れていくしかないのですが、ただ闇雲に一人で練習していてもあまり成長はありません。
それではどうすればいいのかというと、対策としては予備校に通うことです。
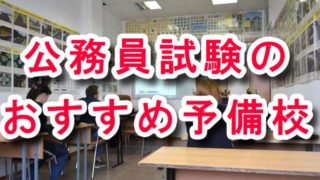
予備校であれば小論文の無料添削がついているケースがほとんどですので、今まで何百何千という小論文の添削をしてきた講師にチェックをしてもらうことができます。
そうすれば自分の小論文がどこがダメなのかよく分かりますので、成長スピードを速く時間帯効率がいいです。
公務員試験は時間すごい長い時間対策に勉強をしなくてはいけませんので、小論文対策にかけられる時間はさほど多くはありません。
短い時間で小論文の書き方をマスターできるように、プロにチェックしてもらうのをおすすめします。
公務員試験の対策をしっかりできるおすすめの予備校はこちらの記事でまとめています。
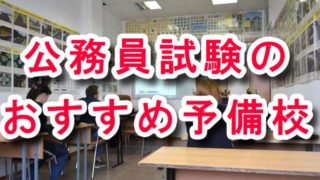
元県庁職員おすすめの通信講座をご紹介
今は自宅にいながらネットで学習できる環境がかなり進化しています。
そのため、自分のライフスタイルや予算に合わせて通信講座を選択する人が多くなっています。
費用も安いですし、いつでもどこでも何度でも見直せる通信講座のオンデマンド学習は予備校よりもかなり便利です。
そんなおすすめ通信講座について興味がある方はぜひ以下の記事を見てみてください。